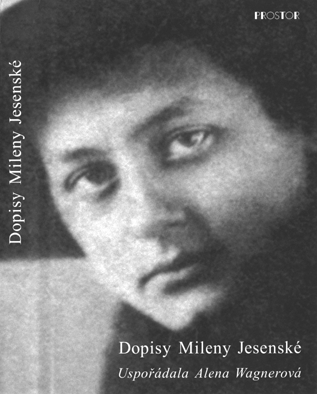 |
「手紙を書くことは、貪欲に待ちうけている亡霊たちの前で、裸になることにほかなりません。書かれたキスは至るべきところに到達せず、途中で亡霊たちに飲みつくされてしまうのです」とフランツ・カフカはミレナ・イェセンスカーに宛てた手紙の中で述べている。手紙、とりわけ恋する人へ宛てて書かれる書簡は、人となりをすべて打明け、内密な側面が露見する。そのため、小説や詩といったある種の虚構性を意識して書かれる作品とは異なり、書簡集、とりわけ恋文は別の次元の関心を誘引する。
作家フランツ・カフカが、ほぼ毎日、あるいは日に数通の手紙を書き送った女性がいる。ミレナ・イェセンスカー。カフカの友人であり、カフカ全集の編者として知られるマックス・ブロートに「過去の人類史において最も素晴らしい恋文の一つに数えられるであろう」と言わしめた134通の手紙から構成される『ミレナへの手紙』。この書簡集によってミレナ・イェセンスカーの名は世界各地のカフカ愛好家に知れ渡ることとなる。
けれどもミレナ・イェセンスカーという女性の実像については「カフカの恋人」という形容に良くも悪くも振り回されていることは事実であろう。20世紀を代表する作家フランツ・カフカ(ミレナは手紙においてフランクと呼んでいる)が恋した女性の一人という説明ではミレナ像はトルゾーになってしまう。というのもミレナが戦間期のチェコを代表するジャーナリストの一人であった側面はあまり認識されていないからである。「ミレナ」像を世界に提示したのは、ラーヴェンスブリュックの強制収容所でミレナと出会ったM.ブーバー=ノイマンの『カフカの恋人ミレナ』であろう。ミレナに関心を持つ読者が手にする初めての資料であるこの作品は、残念ながら、作者にチェコ語の知識が欠落していたこと、プラハ・ウィーン時代のミレナを知らなかったということもあり、資料としてよりも、作者個人のメモアール的な要素が強いことはしばしば指摘されていることである。また長年にわたって、母国チェコにおいて彼女の名がタブーであったという事情も加わって、実質的なミレナ研究はチェコにおいても殆ど行われなかった。このような状況下にあって、ただカフカによる『ミレナへの手紙』が一人歩きして、ミレナ像を彎曲したものにしてしまったのである。
それにしても、ミレナ・イェセンスカー像を再構築することには困難が伴う。恋多き女性、ドラッグ中毒患者、フランツ・カフカの恋人、かたや戦間期のチェコ・ジャーナリズムを代表する女性作家……。彼女を形容する表現は無数にあり、相反するミレナ像を提示しているかもしれない。さらにプラハ、ウィーン、ドレスデンをミレナは転々としており、プラハ時代のミレナを知っている人は、ドレスデンでのミレナを知らないということが起こり、その典型がブーバー=ノイマンの著作である。しかしミレナ自身の著作やミレナに関する研究が次々と公刊されるようになり、より多面的にミレナ像を構成しようという試みが最近出版されている作品に見受けられる(例えば、Mary Hockaday “Kafka, Love and Courage”、Marta Marková-Kotyková “Mýtus Milena” など)。
その中の一冊が、ミレナが友人に宛てた書簡を収録した、いわゆる『ミレナからの手紙』である。カフカによる『ミレナへの手紙』は「カフカ全集」に収められており、邦訳でも読めるが、ミレナがカフカに宛てた書簡は残っておらず、残念ながら、ミレナがカフカにどのような手紙を書いていたかは知ることはできない。カフカ自身がすべて処理したとされ、カフカが返答している箇所でミレナの手紙の断片を窺い知るばかりである(なお、カフカがミレナにチェコ語で手紙を書くように懇願している箇所があり、ミレナはある時期からチェコ語でカフカに手紙を書いていたのであろう)。それに対して、現存している資料をもとに、友人や知り合いに宛て書かれたミレナの書簡をまとめたのが、この『ミレナからの手紙』(“Dopisy Mileny Jesenské” 1998. Praha.)である。25人の友人・知人に宛て書かれた94通の書簡が収録されている。1913年に女優マリエ・ヒュブネロヴァーに捧げた詩が冒頭を飾り、ヴィリー・ハース、マックス・ブロートといったドイツ語作家から、ヤロスラフ・サイフェルト、カレル・マチェイ・チャペック=ホット、アドルフ・ホフマイステル、オルガ・シャインプルコヴァーといった当時のチェコ芸術を代表する名前が連なっている。詳細に検討していくと、カフカの恋人という観点のほかに、一人の才能ある文彩家の発展を辿ることができる。マックス・ブロートへのミレナからの手紙はマックス・ブロート『フランツ・カフカ』(みすず書房)ですでに紹介されており、カフカとの関係に関心のある方はそちらを参照して頂きたい。あまりに紹介されることのなかった、ミレナとチェコ文化界との関係を見ていくことにしよう。
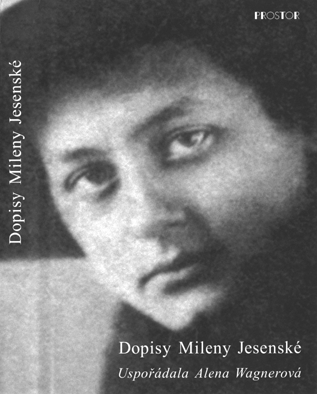 |
まずミレナの文学意識の高まりが感じられる一通の手紙がある。弱冠20歳のミレナが友人である翻訳家オトカル・フィッシェル、文学者オットー・ピックに促がされ、チェコの象徴派詩人オトカル・ブジェジナに面会を求めた手紙である。
「プラハ、1916年8月16日
マエストロ:
…(略)…私は20歳の、あまり目立たない、人の興味を惹くこともない女の子です。でも、できること以上のことを求めようとする精神の苦しみということに関しては、そんなことは関係ないと思います、ええ、その苦しみです。私はきっと自分ができること以上のことを求めているのでしょう――
マエストロ、今まで何も書いた経験のない、そしておそらく何かを書くという才能を持合わせていない――ただ人間的な声を耳にすることを必要とする、人間らしさを持合わせてるだけの若者が、貴方のまったく知らない若者が貴方の家の戸をノックしてよろしいでしょうか。もしできましたら、お宅を訪れてよろしいでしょうか?
ミレナ・イェセンスカー」
その後、職業的な意識の高まりとともに、1919年以降、ウィーンから記事を投稿するようになり、カフカの翻訳もこの時期に行われる。1920−21年にかけては、カフカとの文通が盛んになり、マックス・ブロートにカフカの様子をたずねる手紙などがある。1920年代のミレナの書簡は、雑誌編集者とのやり取りや、ヤロスラフ・サイフェルトとの面会を確認する手紙など、実務的なものがある一方で、友人スタシャ・イロフスカーやマリエ・クヴァスニチカーらとの赤裸々な告白も見受けられる。
しかしながらジャーナリストとしてのミレナ像を如実に浮かび上がらせるのは、雑誌『プシートムノスト』の編集者ヴィリ・シュラムとの書簡であろう。1937−1939年までの30通の書簡が収められた彼との書簡は『ミレナからの手紙』のなかで最も多いページ数が割かれている。ここではオーストリアの記者でプラハに亡命したシュラムに思いを寄せるミレナが、雑誌の運営に苦悩しながら筆を綴っている様子が窺い知ることができる。
「4.8.38
…(略)…編集部は人で溢れかえっているけど、どうやって対処したらいいものか、だって私一人で判断してはいけないんだもの――でも結局はわたしが判断を下すことになるの、だってほかにどうしたらいいか分からないから。誰もわたしに悪いことはしないの(nicht misshandelt)、もう『プシートムノスト』がどうなろうと構わない人ばかり。これほどまでに無関心を装って仕事するって、なんて絶望的なことなの、能力以下のことしかしないって、なんて絶望的なこと、そしてペロウトゥカの無関心さを目のあたりにしたら。まったく、わたしの雑誌とでもいうの?…(略)…」
(原文はチェコ語、括弧内のみドイツ語)
編集活動以外にも、ユダヤ人や共産主義者たちを擁護し、援助するミレナであったが、雲行きが怪しくなってきた1939年11月、今度はミレナ自身が拘留される。そのような状況下でミレナによる現存する最後の書簡から、読取ることができるのは母親としてのミレナ像である。
「[1940年2月]
私の親愛なホンジチカへ
あなたに言いたいのは落ち着いて、明るい子でいるようにということ、私は元気で、あなたに逢えるのを非常に楽しみにしています。また出かけなければならないけれど、それほど長くはならないと思うわ、きっと私を訪問することはできると思うし、お願いだからそうして頂戴、お祖父さんはあなたとそんな遠くまで来れないでしょうけど、ヤロミール父さんは喜んであなたと一緒に来てくれるはず。ホンザ、お父さんに優しくしてね、それからお父さんのこと好きになってね、お父さんは優しい、いい人だから、母さんも父さんのことが好きよ。でも、ホンザ、あなたに一番お願いしたいことは、お祖父さんの願いをすべてかなえて、いうことを良く聞いてあげて頂戴ってこと。お祖父さんは本当に素晴らしい人よ、ホンザ、わたしに対しても、あなたにも美しく振る舞ってくれているわ、あなたにお願いすることはすべてあなたに良かれと思って、素晴らしい未来のためなんだから。ホンジチカ、母さんの言うことを聞いてくれるって言ってくれたら、とっても嬉しいわ、だからお願いよ。…」
以上、ミレナの書簡に簡単ながら触れてきたが、ミレナは幾つもの顔を持っていることに気づく。恋する人、ジャーナリスト、文学を志す乙女、妻そして母。ミレナ・イェセンスカーという人物の特徴はまさにこのような様々な視点が交錯している点にあるように思われる。実生活に根ざした経験と感性がジャーナリストとしてのミレナ像を特別なものにしているのであろう。
もともと手紙は特定の人物に宛て書かれるのが常であって、このようにして不特定の読者に読まれることなど、書き手はおそらく想定していなかったであろう。書簡は、私たち不特定の読者が対象ではなく、恋人、友人、家族といった一人の具体的な対象に向けて書かれている。換言すれば、その人と独自の世界を構築しようと試みているということである。それゆえに、小説や詩とはまた異なって、私たちは書簡に魅了されるのであろう。二人のミクロコスモスに入り込むという禁断の行為を犯して。